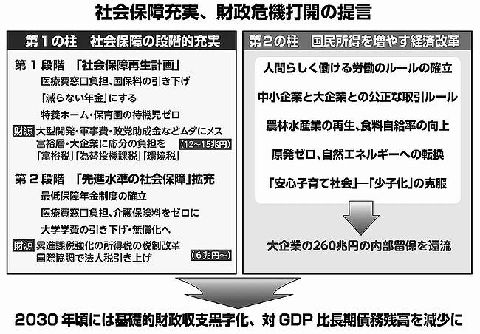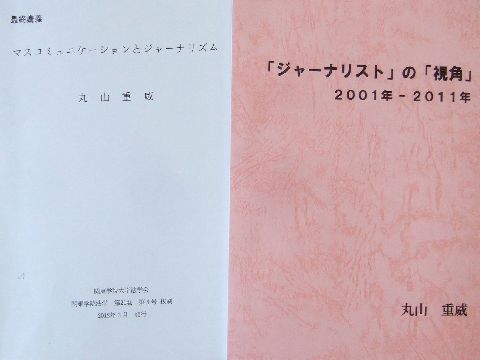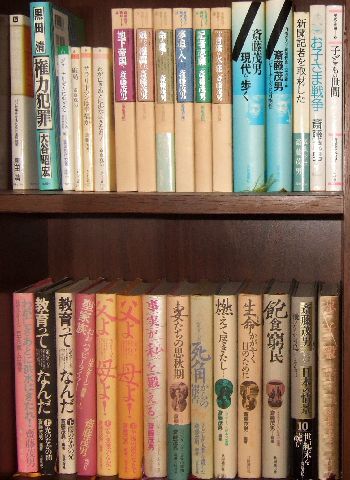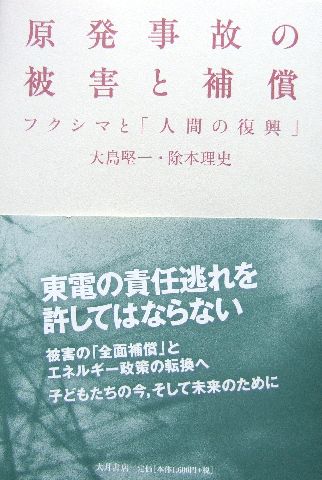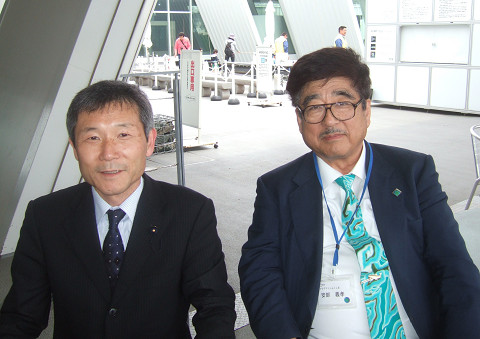約束していたいわき市立総合磐城(いわき)共立病院、いわき市保健福祉部地域医療対策室をたずね、レクチャーを受けました。

共立病院では、大震災後の病院としての対応について病院事務局総務課長から、今年2月7日に「いわき市新病院建設に係る基本構想づくり懇談会」からの提言に基づく新病院基本構想について病院建設室長から、それぞれお話をうかがいました。
現在の許可病床数が828、運用は744、入院患者数のピークは630~640、新病院病床数予定は660程度とのこと。
病床数減は私の根本的疑問ですが、ともかく、「患者を中心とした良質な医療の提供」「地域の医療水準向上への貢献」「地域での対応が困難な医療の提供」という新病院の「果たすべき役割の柱」を、現実のものとする市立病院とするための私たち市民の役割が重要だと思います。

その後、樋渡(ひわたし)信夫院長ともお会いし、懇談しました。
地域医療対策室は、前市長時代に新設された部署です。
実は当時、いわきの深刻な医療実態を把握して政策提言を考えるために、あちこち聞いて歩いたのですが、いわき地方の「医療計画」をつくるのは福島県、医療現場からのさまざまな生データを県や国へ届けるために「通過」するのが保健所で、市役所の中にいわき市医療の実態や医療需要を把握し、この地域の医療をどうするかの政策作成主体がないことを感じていました。
そのしくみは今も変わってはいませんが、地域医療を住民の立場に立って充実するための県の役割やリーダーシップの発揮は、それぞれから強く求められました。
本質的に公的な医療提供を、行政が手放す政策を国策として進められてきたなか、職員のみなさんの悩みはいかばかりかと思います。
地域の医療・介護・福祉提供を一人ひとりの住民のために調整するコーディネートの公務労働すら縮小され、手が出せないのです。
誰がこんな世の中にすることを主導し、手助けをしたのですか? 私はそうならないことを主張し、提案もしてきましたが、これが受け入れられないできたからくりなど、誰か知っていたら教えてください。