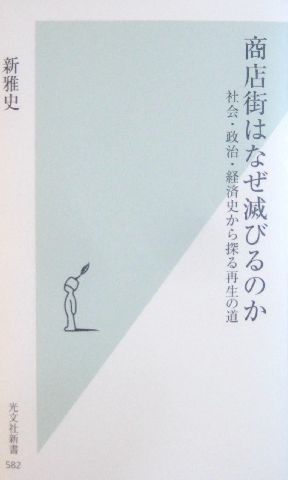党県委員会で会議がありました。
先月27日、県委員会に寄贈された「フクシマの母―フクシマを忘れまい」。
チリ生まれのフランス人画家、ペドロ=デ=レオンさんの大作です。
ペドロさんは、チリのアジェンデ政権時に政権を支える立場で活動され、軍事クーデタ後、命の危機を乗り越えてフランスに亡命されたかた。
党の奈良県委員会が、シンポジウムを開いた同じ会場で個展を開いていたペドロさんと出会って以来、交流が続いていたそうです。
原発をなくすための立場を貫いた福島県の共産党に絵を贈りたいと、3か月かけて書き上げたそうです。
奈良県委員会の支援により、「ペドロさんの絵を福島に送る会」のみなさんが福島県委員会をおとずれてくれました。
贈呈式の際、ペドロさんはこの絵について「私の母に、そしてすべての人々の母に捧げたものです。つまり、それは、この地球において、無知で無責任にしかも慈悲のかけらもなく、われわれの環境を破壊し、貪欲に人々を搾取する政財界、経済システムを告発するものです」と語ってくれたそうです。