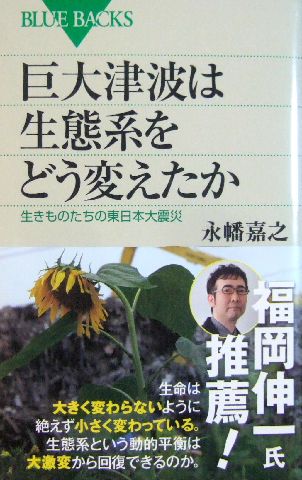事故原発の原子炉の実態すらわからなければ、地震動による被害もわかっておらず、原発事故の原因究明は始まったばかりです。政府や国会の事故調査委員会の検証も途上です。
政府が示したとりあえずの30項目の「安全対策」も、計画さえつくればいいだけで、対策としてとられていません。
地震と津波の学問的知見の根底からの見直しを迫ったのが今回の大地震で、その議論は始まったばかりです。福島原発近くの双葉断層や、井戸沢・湯ノ岳断層の調査すらこれからです。
全国の原発が事故を起こした場合の放射能被害の予測、住民避難の計画すら立てられていません。事故時の対処はまったくできない状態です。
いまだにまともな原子力規制機関が存在していません。原子力安全委員会、原子力安全・保安院は、今回の原発事故に責任があるにもかかわらず、なんの責任もとっていません。
原発再稼働にはいっぺんの道理も科学的知見のかけらもないのです。
こういう状態で、野田首相はきのう、「万が一、全ての電源が失われるような事態でも炉心損傷は起きない」と、新たな安全神話を振りまき、「国民生活を守る」ためだと言い放って、大飯(おおい)原発3、4号機の再稼働に突き進む異常な姿勢を明確にしました。
自分で何をしているのかわからない民主党政権の極地です。財界・電力会社の言っていることを忠実に実践することが政治の仕事だと信じきっているようです。こういう人たちが「国民生活が第一」と言っていたのです。
消費税増税しかないかのような話もそうですが、大手マスコミに踊らされるのもいい加減ヤメにしませんか。
いまは、稼動ゼロから原発ゼロに政治決断する時です。その決断を迫るのが私たち国民・有権者です。
写真はいずれも今年1月30日の現地視察時のもの。