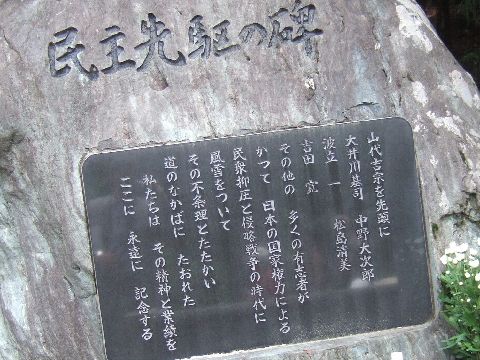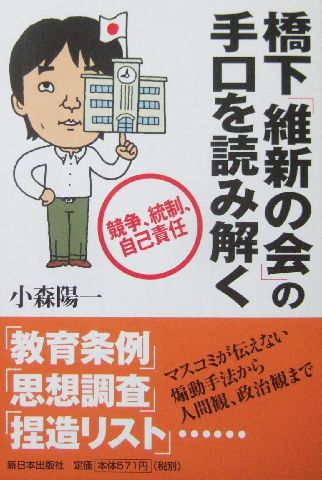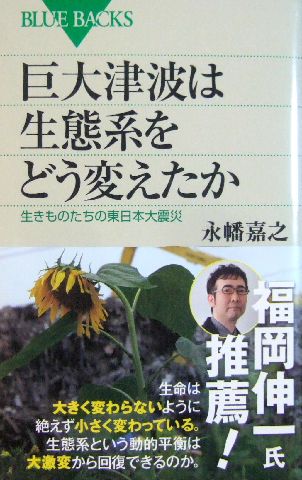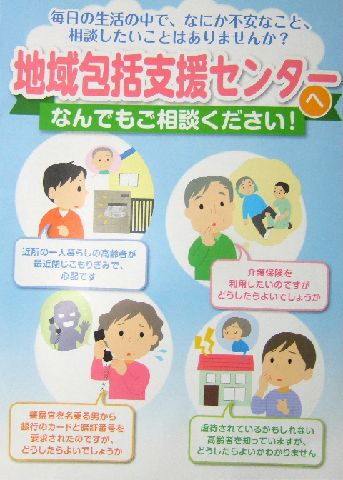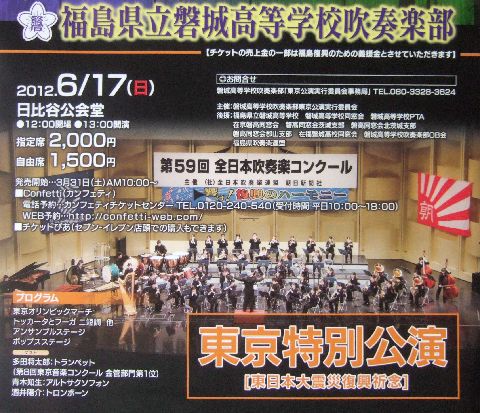恥ずかしながら、あした、原発問題福島県民連絡会の今年度総会で、「県政の状況」を報告することになっていたことを思い出し、ほとんど付け焼き刃的に準備する時間にあてることとなりました。
震災時から8か月は議員でなく走り回り、昨年11月下旬の県議選で県議2期目を務めるようになってから7か月。県政においても県議会においても「オール福島」の動きが進んでいる一方で、原発事故が「人災」だと言うことを避ける知事。
そして「オール福島」の声に応えようとしない国と東電の姿勢。それどころか「原発再稼動」と「消費税増税」。
この打開がなんとしても必要です。
きょう開会した南相馬市議会では、大飯原発再稼動に反対する意見書と消費税引き上げ反対意見書が採択されました。7日に開会した川俣町議会でも大飯原発再稼動反対意見書が採択されています。
両議会とも県内原発全基廃炉の意思をすでに表明しています。
ちなみに、福島県内では、59市町村議会のうち46市町村議会で全基廃炉を求める請願採択・意見書採択・決議がされています。
いわき市議会では、自民党系議員10人の「志道会」,同じく自民党系7人の「政新会」、そして東北電力労組出身の議員が所属する3人の「つつじの会」が賛成せず、圧倒的多数の市民の願いである「県内原発全基廃炉」の意思を示せないでいます。
全基廃炉の請願署名が進められており、今年9月には市議選です。市民の意志を示せない市議会にいつまでもしておくわけにいきません