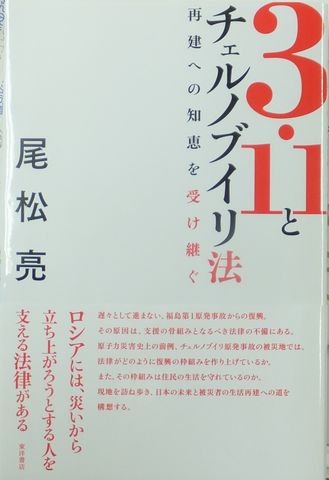6月18日開会予定の6月定例県議会へ向けた県当局の補正予算・復興関連事業の進捗について説明を聞く政調会でした。
県議会各会派を県当局に入れかわり立ちかわり来てもらいます。
商工労働部、保健福祉部、企画調整部、総務部、土木部、農林水産部、生活環境部、企業局、教育庁の順でした。
予算議会後の最初の補正で、国庫の追加決定をふまえ、除染の推進、津波被災住宅の再建支援、地域医療の復興に要する経費など、調整中ではありますが、500億円後半台の予算となりそうです。
原発震災3年目に入り、被害そのものが広がり、深刻化し、複雑化しているなかでの補正であり、復興予算だけでなく、復興関連事業の進捗や今後の具体的とりくみについてただしました。
昼休みには県議会消防協力議員会の役員会、政調会後の夕刻には、党県議団として、橋下徹大阪市長の発言に抗議し撤回を求める声明の記者会見をしました。