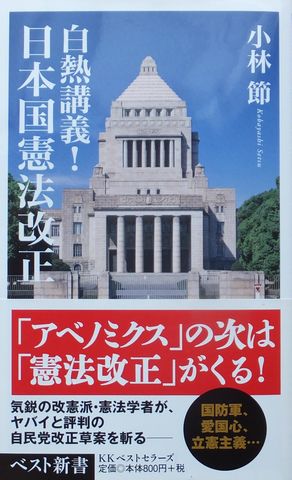浜通り医療生協の四倉(よつくら)地域にある班主催の勉強会に「助言者」として呼ばれて参加しました。
テーマは「いわきの介護について 老いを楽しく!」。
中身は介護保険制度のしくみと、いわき市内の高齢者向け施設についてです。
なので、話をするメインは医療生協の「居宅介護支援事業所」の職員2人でした。
質疑応答になると、親などの介護で今現在の疑問が次つぎと出されます。介護認定のこと、その認定によって受けられるサービスの違い、認定を受けても介護の面倒を受けたくない親、民間事業者がもうけ本位にしているために受けた「被害」、などなどです。
私の感触から言うと、介護保険制度が浮上してから15~16年、ずっと同じことを議論し続けている感じです。その根底には、介護が必要な人が、必要な介護が受けられない制度そのものにあります。
参加者から、「けっきょく、これだけ不都合な制度なんだから、この制度に面倒を見てもらう必要がないように、健康づくり活動を医療生協として続けることではないか」という意見。
そのとおりではあるのですが、そうはいっても、介護制度は必要だと思います。いつでも、どこでも、だれでもが、必要な介護サービスが受けられる制度にしなけれはなりません。医療もいっしょです。