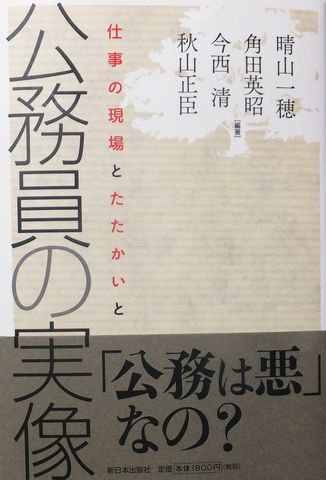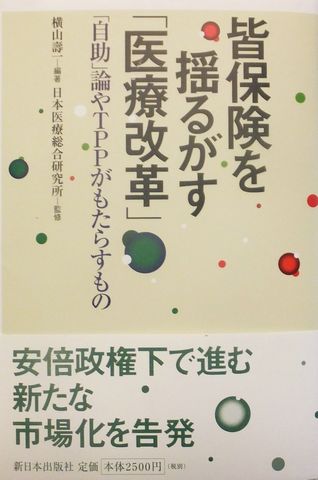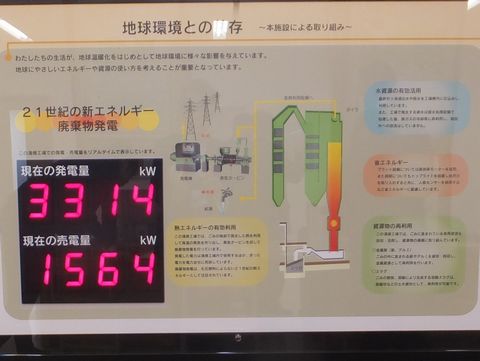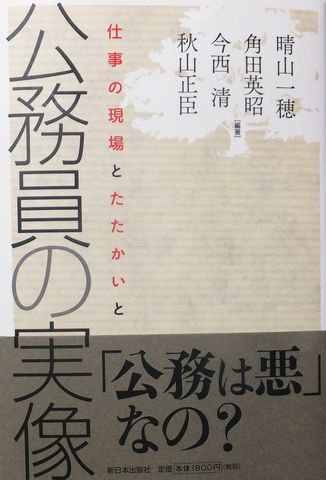
『公務員の実像』(晴山一穂・角田英昭・今西清・秋山正臣編著、新日本出版社)を、先だっての北海道視察の際、移動中に読みました。
現在の行政のあり方や公務員のあり方に、「問題なし」という人はいないと思います。
国民が抱くそうした率直な疑問や批判と、意図的な「公務員バッシング」と言われる非難や公務員の権利・利益を脅かす動きは、まったく違うものと私は思います。
もともと公務員の「公」は、個々人の私的利益の共通の利益である「公益」のための事務処理を社会化し、社会的規模で組織編成するところに生まれる社会公共概念です。
だから、社会が複雑化すればするほど、公務・公共業務は増えるのが必然、というのが私の理解です。「公」は「私」と対立するものではなく、むしろその延長線上にあるはずです。
そもそもの公務・公共業務の検証すらなく、公務員給与の大幅削減を強行したり、「官から民へ」とか言って、公的な事務・事業を民間部門へ移すことによって、公務員が大幅に削減されたり、免職されたり、一方で、「政治主導」のもとで、首長に従わない公務員を「民意に逆らう」反国民的な存在として威圧したり、排除する動きもあからさまです。これらの動きによって、国民の疑問・批判が解決されるはずがない、と私は思います。
本書は、現場で直面している問題や悩み、仕事や国民・住民への思いを公務現場の職員が率直に語り、この現実の仕事や姿への理解を深めることで、国民と公務員との連帯、絆を回復し、強め、国民の利益を拡大する行政、政治の実現をめざして企画されました。
第Ⅰ部では、被災地での大震災直後からの仕事(第1章)、生活保護・自治体病院・国立病院・国民健康保険窓口、ハローワーク現場(第2章)、維新の会によって変質させられる大阪市役所、社保庁解体により分限免職させられた職員の今(第3章)、公務の民間化・非正規化にさらされる指定管理者制度、保育現場、登記事務現場、消費者センター、「官製ワーキングプア」の実態(第4章)が現場から発信されます。
そして第Ⅱ部で、公務員とはどういう存在なのか、公務が公務員によって担われることの意味がどこにあるかを示してくれます。
ともかく、端的に言えば国民の「私的」な幸せを実現するために政治と行政という「公務」はあるわけで、この幸せを実現する方向に変えることがほんとうの行政改革であり、公務員改革です。そのことの理解なしに、私の言っていることが正しいとばかりに行政批判をしていても、前には進まない、という気が私にはしてなりません。