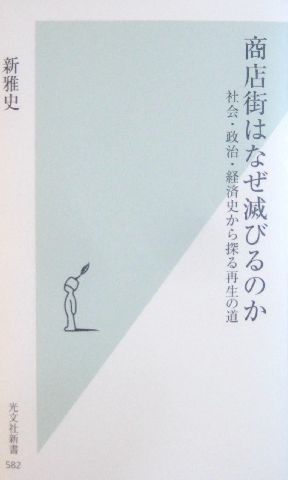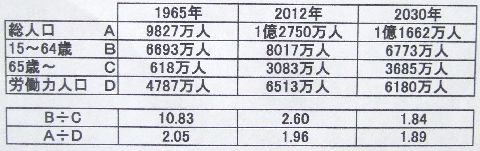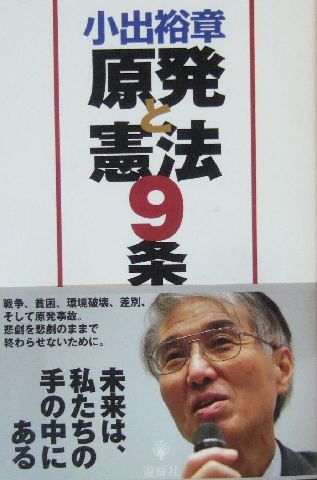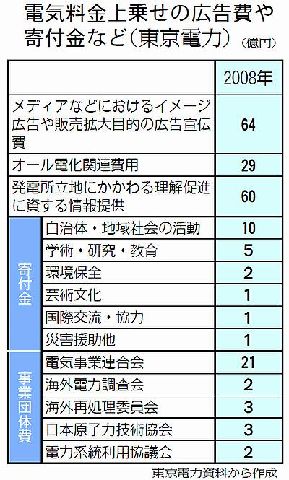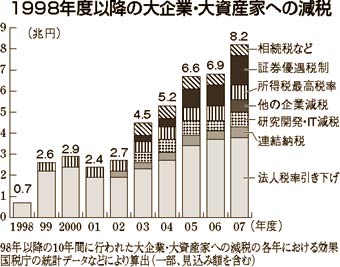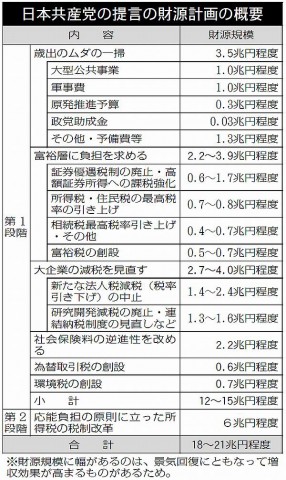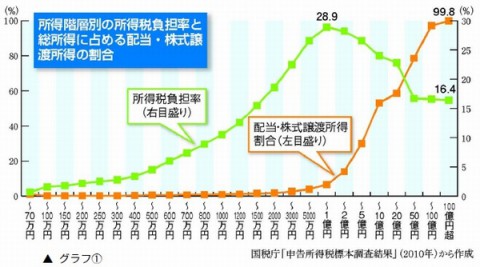『商店街はなぜ滅びるのか』(新雅史[あらた・まさふみ]著、光文社新書)を読みました。
県庁から家に帰る途中のラジオだったと思いますが、この本を絶賛する話を聞き、手にしたしだいです。
著者はまだ30代で、実家は酒屋、社会学を10年以上学んでいますが、「将来どのような社会になるのかまるで想像できない」、「経済的な理由もあるが…社会全体の先行きが見えないという理由」で「いまだに結婚もできていない」という境遇で「大学の非常勤講師で何とか糊口をしのいでいる」人です(「あとがき」)。
現存する商店街の多くは20世紀になって人為的に創られ、その繁栄と衰退を著者なりに解明してくれています。
そして商店街の再生のために、「地域で暮らす人々の生活をささえ、かつ地域社会のつながりを保証するために存在する」「規制」を強化すべし、と提起します。