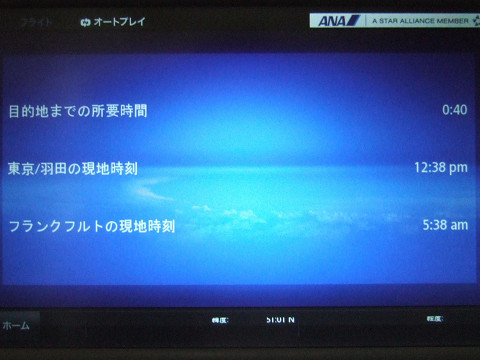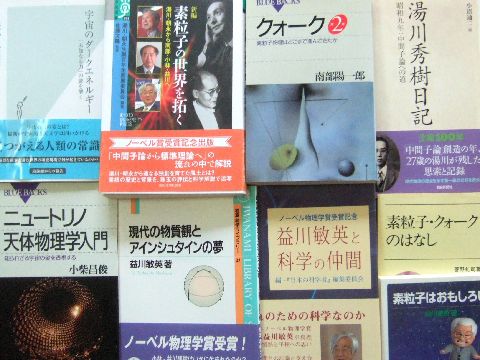ドイツ訪問の目的は、再生可能エネルギー普及に国・自治体・住民がそれぞれ主体的にどうかかわっているかを調査することです。
最初にたずねたのは、カールスルーエ市内の「ゴミの丘」を「エネルギーの丘」に変えた現場。
ドイツ在住16年で、ジャーナリストの松田雅央(まさひろ)さんが案内してくれました。
簡単に言ってしまうと、ゴミ埋立地の上に風力発電施設を作り、埋立地の斜面は太陽光発電に活用し、ゴミから発生するメタンガスの熱も活用する、というものです。
カールスルーエ市では、風力発電の8割が市民の出資で、市民一人ひとりがエネルギー事業者という発想です。
その後、人口が2000人ほどのブライトナウ村へ行き、ジョセフ村長の案内で村内を回り、水力発電業者のカイザーさんの話を聞いたり、村長自身が力を入れるバイオマスの現場を歩きました。
いまこの村は、電力需要の170%がバイオだそうです。住民参加型がカギのようです。
来年がどうなっているか、ぜひ見に来てほしい、と訴えられました。