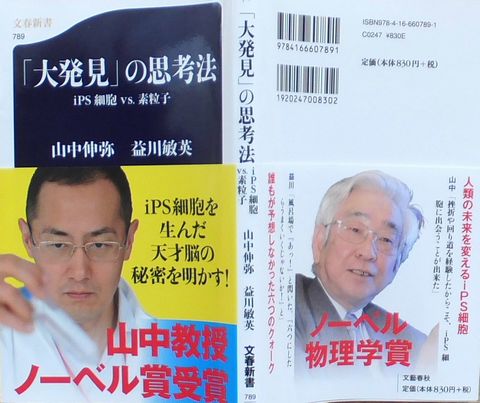午前中から、常磐(じょうばん)・内郷(うちごう)・好間(よしま)地域の党後援会合同の芋煮会がありました。
会場はいわきの名峰・湯ノ岳のふもとの丸山公園の奥にある湯ノ岳山荘前の広場。
衆院福島5区予定候補の吉田英策さん、市議のみぞぐち民子さん、そして宮川さんといっしょでした。
野外での焼きたてサンマ、トン汁、おにぎり、漬物、柿などおいしくいただきました。
午後は「50年党員・永年(30年)党員顕彰の集い」。
安保闘争があり、第二次世界大戦後の党の綱領を決めた1961年直後から党活動を続けてきたみなさんが50年党員、そして、共産党排除の日本政治の展開が進む契機となる1980年の「社公合意」、そして今に連なる社会保障切り捨て政治が始まる「臨調・行革」の1981年直後からのみなさんが30年党員。
みなさんがひとことずつごあいさつされたのですが、それぞれの人生と歴史ですから、重いし励まされることばかりです。私は開会のあいさつ。
ちなみに私は京大入学直後の1979年に入党し、33年目です。