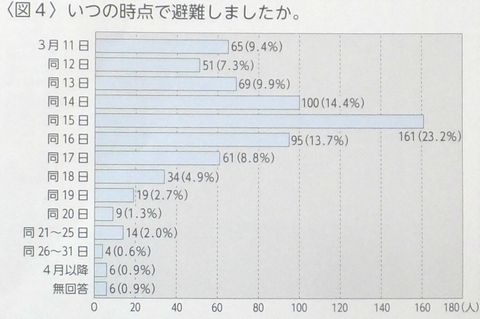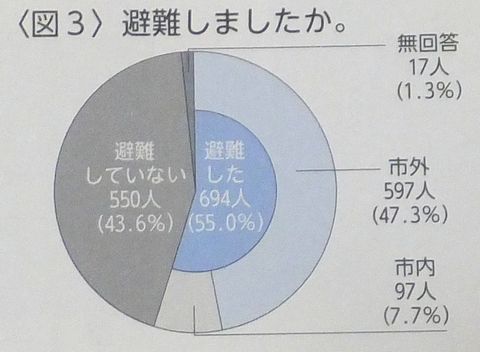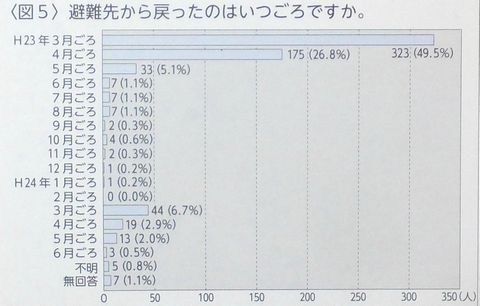いわき市議選時、いろいろお世話になっていたにもかかわらず、その後の日程でたずねられなかったかたがたをお詫びを兼ねてたずねました。
ある会社の営業所では、原発震災の影響で年間7000万円の減収。本社を通して東電に損害賠償を請求し、営業所としては独自の努力で損害の半分は回復しているものの、いまだ、賠償金でつながざるを得ない、という実態です。

別の事業所では、昨年の県議選時から「しんぶん赤旗」日曜版を購読していただき、「届くとすぐに食い入るように読ませてもらっている。ほかの新聞では何も書いていないことで大事なことが書いてあって、領土問題はすごくわかる」と。今も自民党衆院議員のジャンボポスターが室内に貼られています。

いわき市暮らしの伝承郷で「樹・石・草・常磐会展示会」をしていることを地元紙で知り、寄りました。
自宅から車で5分ほどのところで、いつでも行けるだけに、意外と行かないところなのです。
いわき自立生活センターにも寄らせていただきました。障がい者のかたがたの暮らしをささえるNPO法人ですが、昨年の震災直後から県・国・市へ障がい者が置かれた実態に基づいで要望を届け続けています。

日常的な「社会的弱者」が、災害時に「災害弱者」として、命を含めてたいへんな目にあわされ、行政的支援がまったくなくなってしまった現行制度は、根本的見直しが必要だと、つくづく思います。
障がい者や高齢者の暮らしを支えることは基本的に民間まかせにし、行政は撤退するしくみは憲法の考え方に反するとして、私たちは、国・行政の責任あるしくみを求め続けました。
大震災の教訓ははっきりしていると私は思います。