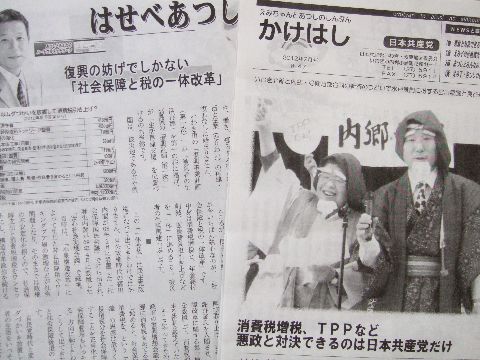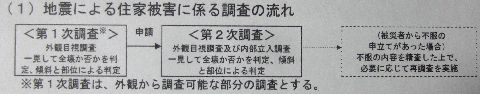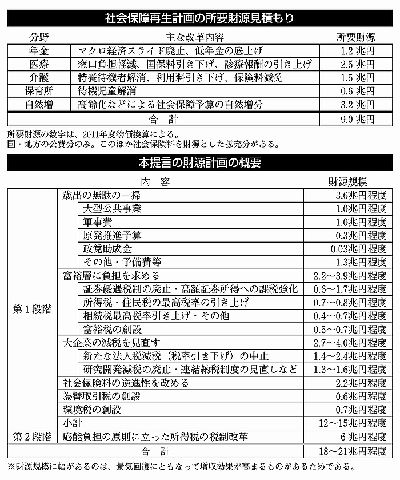午前中、県議団控室に、双葉郡から福島市内の仮設住宅に入居されている、「永続的生活保障法を求める原発被災者の会」のみなさんが要望に見えました。
国会で審議される福島県復興再生特別措置法案は、県知事の提案権を盛り込み、これを活用して一人一人の被災者の生活支援・保障を国にさせることもできます。
そうしたことや、「税・社会保障一体改革」など、いろいろな話。
午後は「子育て・健康・医療対策特別委員会」。
子育て支援担当理事、教育長説明後の質疑、40ページにわたる各部署からの事業説明後の質疑を行ないました。
私は、県教育委員会による「放射線等に関する指導資料」が、「はじめに」で「原子力発電所の事故による放射線等の問題が被害の状況を更に悪化させ、放射性物質の放出は、大気や土壌等の汚染をはじめ、食糧、ひいては健康への影響等、生活のあらゆる面で多くの不安をもたらしました」と書いてあることがどう反映されているのか聞きました。
浴びる必要のない放射線を浴び、日々、放射線の影響を恐れながらの暮らしを強いられ、その原因が原発事故であり、その原発を地震国日本に建て続けたことにあることにいっさい触れてはいないからです。
間違ったことは書いていないが、必要なことが書かれていない指導で子どもたちは正しい知識を得られるのでしょうか?
かみ合った話をしてくれることはありませんでした。
自民党の委員が私の話に賛同する意見を言ってくれました。