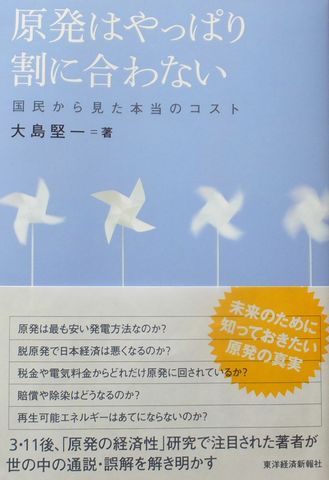きょう2月1日は、「しんぶん赤旗」の創刊85周年の日でもあります。
85年前(昭和3年)は、25年前に亡くなった父が生まれた年でもありますが、男子普通選挙法による最初の総選挙があり、京大の河上肇教授が辞職を迫られ、辞任した年でもありました。
当時は「せっき」と言っていましたが、「生活を保証せよ」「民主的議会を作れ」「虐殺戦争に反対」など、総選挙に向けた要求が掲げられていました。
きびしい弾圧のなか、戦前は187号まででしたが、戦後の党の活動再開とともに再刊され、日刊紙はきょうで2万2320号です。
きょうの紙面では、早野透桜美林大教授が「『日本帝国主義の戦争準備と斗へ!』と書き、『一人の兵士も送るな』と反戦を貫いた紙面は、やはり歴史への尊い貢献といっていい」と言ってくれています。
そういえばきのうの訪問のなかで、「レッドフラッグぐらいの名前にしてもらえれば、読んでみようか、と思われるんじゃないか」という声もありました。
党名同様、この日本社会の歴史の中で刻んできた名前を知っていただく私たち自身の努力の重要性をまた痛感したしだいです。
ちなみにわが家で購読している「朝日」は4万5526号、「福島民友」3万9014号です。
きょうはいわき市主催の第21回「暴力追放いわき市民大会」に参加しました。
「最近の暴力団情勢と不当要求に対する対応」と題した県警本部による講演もありました。
暴力団による資金調達活動の多様化に伴う「不当要求」の実態もビデオで上映され、悪質巧妙さが進んでいること、なにより、「相談」がキーワードだ、と強調されました。