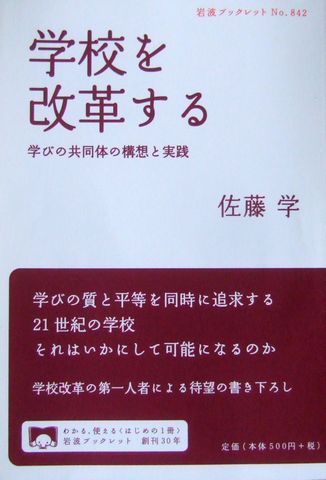常磐・内郷地域の知り合いの新盆を迎えたお宅をたずねました。
お一人の遺影は、プロの写真家が撮った白黒写真で、今にも口角泡をとばす寸前に私には見えました。
というのも、おととしまで、定期的にせいきょうクリニックに仲間たちと通院し、私を見かけると必ず声をかけてくれ、口角泡をとばして話をしてくれていたのです。
内郷(うちごう)駅前には回転櫓(やぐら)。きょう、あすと、夕刻には盆踊りです。内郷の生まれ育ちの私は、近所の仲間たちと毎年のように繰り出していた「いわき回転やぐら」の盆踊り大会。なつかしい。
これは、「いわき百科事典プロジェクト」の「いわき回転櫓盆踊り大会」のページに掲載されている去年の様子。