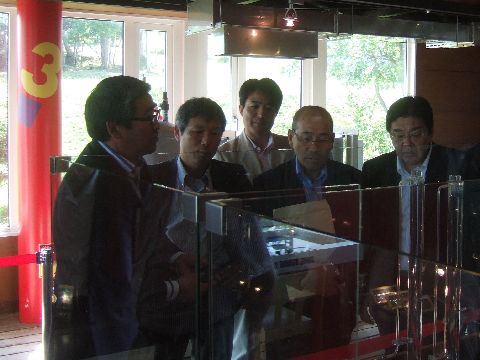盆の入りです。
私の出身職場である浜通り医療生協職員で、亡くなられたご親族が新盆を迎えるお宅を、職員でもある妻とたずねました。
職員の職場は、病棟、居宅介護、病院厨房、診療所外来、短期入所介護施設と様ざまでした。ほんとうにいろいろな職種の人たちに支えられ、患者・利用者に寄り添うのが医療生協の職場です。
原発震災後も職場を守った職員に感謝しつつ、自宅にもどった精霊に手をあわせました。
今年は格別の思いで迎えるお盆であり、そしていろいろな人生に触れる機会でもあります。
娘が夕べ、帰省し、興奮して迎えたペロは、熟睡。