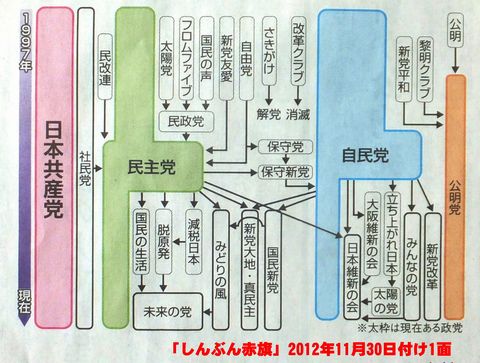けさ、県庁へ行くと、控え室の近くの委員会室からたくさんのダンボール箱を台車で運び出す職員たち。県選挙管理委員会から市町村へ送り出す総選挙用の投票用紙でした。
きょうも一日、来週6日予定の代表質問へ向けた「質問とり」。
順調に始まったかと思うと、簡潔明瞭と私が自覚する質問が複数の部や課にまたがると、沈黙が続く場面が時どき。
答弁書を準備するのをどちらが責任を持つかが問題になるわけです。質問者の責任ではまったくないと思います。
今回の質問では、「県職員はその業務の実施だけでなく、住民要求を把握し、その要求を反映させる政策形成も期待されてい」るし、大震災からの教訓を県職員の人材育成へ生かすべきことを提起しますが、「タテ割り」行政に加えて、「行革」の名による職員削減で、県行政現場を疲弊・劣化させている弊害が浮き彫りだと私は思わざるを得ません。