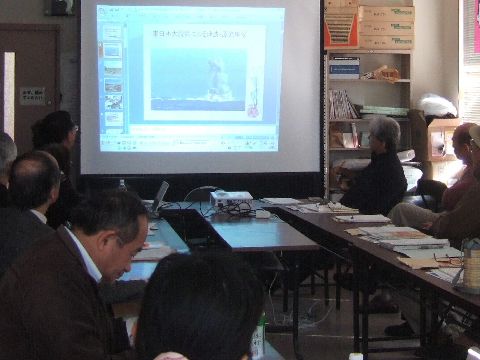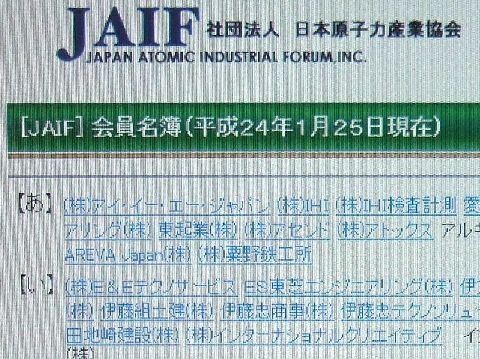94年1月21日に参院で「政治改革」法案が否決後、当時の非自民=連立与党=小選挙区推進派は法案の「生き返り」を企て、1月27日に両院協議会を開催したものの決裂。
衆議院で可決した法案が参議院で否決され、両院協議会も決裂した以上、法案は廃案にするのが議会制民主主義の原則です。
ところが1月28日、当時の土井たか子衆院議長が動き、「トップ会談による蘇生」の道筋がつけられました。

マスメディアが細川首相と河野自民党総裁とのトップ会談をけしかけていたのです。密室談合後、法案は強行されました。
そして小選挙区制が導入されて18年。直近の2回を見ても、05年総選挙では自民党が47.8%の得票で73%の議席、死票は有効投票数の48.5%3300万票、09年の政権交代選挙では、民主党が47.4%の得票で73.7%の議席、死票は同じく46.3%約3270万票。
当時のトップ会談に立ち会った森喜朗元首相が「政治の劣化の要因は…根本的には小選挙区制に原因がある」(「自由民主」2011年11月22日付)と言い、渡部恒三民主党最高顧問が「小選挙区制は間違いだった」(2月23日、超党派の「衆院選挙制度の抜本改革をめざす議員連盟(略称=中選挙区制議連)」での代表世話人あいさつ)と言うのが小選挙区制度です。
この制度によって、国民のために働いているのかもわからず、民意を通そうとしているのかもわからない議員を生み出している問題を、議員の数の問題にすり替え、議員自身が「身を切る」などということも大問題です。
「身を切る」と言う以上、議席は特権であり、自らのものなのだ、という考えが横たわっています。
しかし議席は、国民から負託されたものです。議員の数を減らすことは、「身を切る」のではなく、国民の代表の数を切ることです。
多くの政治家が国民のために働いていないからといって定数削減すれば、さらに民意を反映しない悪循環をつくりだします。きのうの日刊「しんぶん赤旗」で、大東文化大学の井口秀作教授がインタビューに答えてくれています。
きょう付け「しんぶん赤旗」は、小選挙区導入に旗を振り、害悪がはっきりしているのにいまだ無反省の大手メディアの実態を報じています。