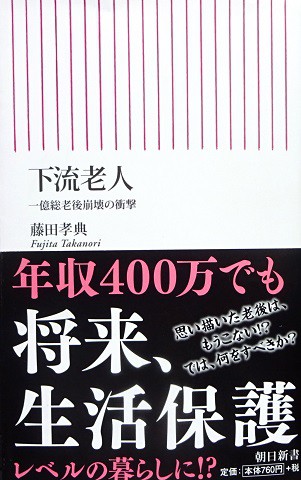きょうは浜通り医療生協の定例理事会。病院内では「ミニ原爆展」の展示があります。
午前中は9月議会での質問を構想しつつ、月刊通信の「かけはし」原稿は県議会全員協の東電質疑の様子をまとめました。以下、その原案です。
8月5・6日と、東京電力と政府機関を呼び、県議会の全員協議会がありました。
私は5日、共産党県議団を代表して東京電力に対する質疑をしました。
質疑時間が9分間なので、答弁準備をしていなかったといった言い逃れがないよう、議会事務局を通し、17項目にわたる詳細な質問を通告しました。
なおかつ、聞きたい項目への東電の現時点での考え方を議会の場で明らかにしておく、というスタンスをとりました。
最初に聞いたのは福島第二原発の廃炉決断についてです。
経産省は、2030年には30基台半ばの原発を稼働させるつもりです。
その年に稼働40年を越えないのは20基しかなく、40年を超える第二原発を含めて政府が稼働させようとしていることは明らかです。
そこで私は、第二原発再稼働を期待しているのか、ということと、「この場で事業者として廃炉を明言すべき」と迫ったのです。
東電社長の答弁は、「国策民営という国のエネルギー政策にのっとってきた」と言いながら、「未定」と繰り返しました。
福島県民の願いを踏みにじり続けている自覚はまったくありません。
事故は人災かも問いただしました。東電は2013年3月の「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」の中で、「原子力部門は『安全はすでに確立したものと思い込み、稼働率等を重要な経営課題と認識した結果、事故の備えが不足した』との結論に至」った、としています。
また事故の年の4月、当時の副社長が「個人的には人災だと思う」と言っていたことも示しました。
これに対し社長は、「人災なのか天災なのか、正直言って真剣に考えたことはない」と言い放ちました。
私は「津波対策を怠った過失責任は明白」と迫りましたが、「折しもこれから起訴され、裁判所で判断が下される」と逃げたのです。
加害者責任のかけらもない、と言わざるを得ません。
こうした事業者に寄り添い、福島県民を切り捨てる安倍政権の原発再稼働・原発推進政策ノーのきっぱりとした審判が必要です。